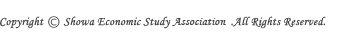HOME > 理事長室より
- 最新ナンバー
- バックナンバー
- 2024年04月
- 2024年03月
- 2024年02月
- 2024年01月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年09月
- 2023年08月
- 2023年07月
- 2023年06月
- 2023年05月
- 2023年04月
- 2023年03月
- 2023年02月
- 2023年01月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年09月
- 2022年08月
- 2022年07月
- 2022年06月
- 2022年05月
- 2022年04月
- 2022年03月
- 2022年02月
- 2022年01月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年09月
- 2021年08月
- 2021年07月
- 2021年06月
- 2021年05月
- 2021年04月
- 2021年03月
- 2021年02月
- 2021年01月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年08月
- 2020年07月
- 2020年06月
- 2020年05月
- 2020年04月
- 2020年03月
- 2020年02月
- 2020年01月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年09月
- 2019年08月
- 2019年07月
- 2019年06月
- 2019年05月
- 2019年04月
- 2019年03月
- 2019年01月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年09月
- 2018年08月
- 2018年07月
- 2018年06月
- 2018年05月
- 2018年04月
- 2018年03月
- 2018年02月
- 2018年01月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年09月
- 2017年08月
- 2017年06月
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年02月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年09月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
- 2015年03月
- 2015年02月
- 2015年01月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年08月
- 2014年07月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年06月
- 2005年05月
- 2005年04月
- 2005年03月
- 2005年01月
Vol.8-05 黒いダイヤの復活化
黒いダイヤ、石炭
黒いダイヤともてはやされた石炭産業が、日本から姿を消してから半世紀が経ちました。原油が石炭に取って代った画期的時期が、過去の遺物として記憶に新しいのですが、その原油価格の高騰で、今、石炭産業が見直されてきました。しかし今日、世界をとりまく環境の悪化の張本人であるCO2、二酸化炭素の排出抑制で世界が躍起になっている状況で、直ちに石炭を代替エネルギーとして復帰させる機運には相当な抵抗があります。視点を変えて、無尽蔵にある石炭の有効な活用をもっと探求していく必要があります。石炭を見直して、黒いダイヤとして資源的に大きく浮上させることが、現代に課せられた大きな使命の一つではないでしょうか。エネルーぎーとしての資源的価値を含め、多面的活用は魅力に富んでいます。日本の技術と研究成果が発揮されて、石炭の存在価値が大きく浮上してきました。当面、エネルギーとしての石炭をもっと見直すべきであります。早晩、眠っている日本のマーケットもその動向に注目してくるでしょう。
エネルギーに関しては、少くとも石炭の燃焼から出る厖大な二酸化炭素の処理方法に、更に革命的な道筋と、経済合理性が確立されない限り、その活用と効果は最大限に発揮されません。石炭からでる二酸化炭素を地中深く注入する方法が考案されています。例えば中国を舞台に今、火力発電から排出される二酸化炭素を油田に注入、封じこめて原油を取り出し易くする画期的な事業が行われようとしています。
これは大量の二酸化炭素を地下に貯留する新技術で、これによって大気の中に排出される量を事実上ゼロにすることが可能とされています。これ自体は事業としては利益が出ませんが、報道によると、舞台を中国の黒竜江省に移して、ハルピンの石炭火力発電所で応用します。同発電所近くにある大慶油田にこれを運び、同油田に注入、貯留してそのメリットを実現する計画です。
大慶油田にある油質は、もともと粘度が高いため、取り出しに困難な状況にあります。二酸化炭素の特性を利用して、この原油の粘度を軟化させることが出来ます。大慶油田にこの二酸化炭素を注入、混入することによって原油の粘度が低下し、原油を容易に採油しやすい状況を作り出し、二酸化炭素を効果的に活用する方法です。原油と石炭の、大規模な混合利用であります。
ところで石油も化石燃料であることに変りはありません。要は二酸化炭素の地下の貯留技術がいかに拡大可能かが問題です。同時に、この厄介者の二酸化炭素そのものを、何らかの方法で有効な素質に変えられないものか、研究、開発する努力がもっとなされてしかるべきであります。石炭自体の有効活用の、具体的方策の研究と成果が依然として課題になります。石油に代わって石炭の存在価値が黒いダイヤとして浮上してくるか否か、ひとえに人知にかかわっています。それは可能でしょう。高騰する原油に代わる石炭の地位は、相対的に大きく浮上してきました。
ここで重要なのは原油の価格高騰を喰い止めるための、石炭の活用と復活が重要であり、短期的には、中国での実験が成功すれば、二酸化炭素の処理と、エネルギーの絶対量を一部確保する一応の手だては見込みが立ちました。いずれにしても石油にしろ、石炭にしろ、これを単に動力、熱エネルギーの資源として燃してしまうだけでは余りにも知恵がなさ過ぎます。原油も石炭も、資源としてもっと広範囲且つ有益に使用する資源として認識し、見直す必要があります。そして一般的には、二酸化炭素そのものを、地価に深く貯留する考案と同じように、有効に活用する手立てを発見することではないでしょうか。
日本には経済的な採算から、止む得ず閉山となった良質の石炭資源が豊富にあります。短期的には原油の代替資源として競争力を高めてきましたが、これの新たな発掘と活用が目下の課題であります。単にエネルギーとしてでなく、他面的且つ画期的な活用方法を案出すべく研究する余地があります。日本の技術と学術的知識を以って、二酸化炭素の除去にばかり気を奪われるのではなく、逆に他の応用を広く研究、開発、考案し、世界に先がけて石炭の有効活用に官民挙げて努力すべきであります。日本の石炭掘削技術は最高水準を行っており、これを又無にしてはなりません。原油の狂的高騰を機に、世界経済は物価高騰の危機を招きかねません。これを回避して経済を安定化させることは、我々の責務であります。もとよりエネルギーの大消費型経済の枠組みの改善を行い、エネルギーの小消費型の経済社会を目指していくことが肝要であります。
株価は世界的に大底?を打ったか。
サブプライム問題は世界に深刻な打撃を与えていますが、それがもたらす金融資本市場への影響は最終的局面に入ったとの認識を、私は五ヶ月前に予告しました。当局による国際的な迅速且つ、大胆な金融、財政政策が、徐々にその効果を期待しうる段階に入って来ていることは一縷の光明であります。株式市場は、もとより激しい上下の振幅と繰り返しつつ急落してきましたが、先見性を発揮して最悪の事態は可成り織り込んできていると判断しました。時期尚早を覚悟の上で、そのことを勇気を以って発言し、各位にお伝えしました。ちなみに打撃を受けた日本株式に於いても、金融株は極めて顕著であります。例えば、みずほは平成十八年六月に付けた一〇三万二千円から急落し、今年三月十八日には三六万の安値をつけました。私はみずほの四五万円は売り込まれ過ぎと判断し、四十万前後は猛然と買い方向を打ち出しましたが、皮肉にも暴落の痛手は深く、買い余力のない状態は各位とも如何ともしがたき状況です。先に行われた当会の講演親睦会でも小職は敢えて発言し、株は既に大底を打って買い方有利の状況と話しました。まだはもうなり、もうはまだなりと言う格言もあるとおり、この道の世界は予断を許しません。しかしどこかで決断をしなければならないでしょう。企業経営も然りであります。経済行為にはリスクを伴います。
そこで世界的な時流に乗っていくには、依然と指摘される東京株式市場の閉塞性、閉鎖性です。敢えて後進性というべきでしょうか。「東京株式市場の後進性」は、今の日本社会を象徴するようなものであります。後進性といえば問題の焦点が、その透明度を増してくるかもしれません。日本を取り巻く経済の後進性が、今の世界の動向と水準から、容易に理解されてくるでしょう。東京市場の世界に向けた開放性への法整備と、取引きの各種の規制の改革、撤廃といった、解決すべき重要な課題があります。時代にそぐわず放置されたままに旧態然としており、それらが外国資本の日本への円滑、透明な流入を妨げ、大きな障害となっています。
日本の株式市場が機能的に、世界に通じたマーケットでなければ、世界の資金は呼び込めません。依然として旧態然の観念に縛られた東京の株式市場、無意味で百害あって一利なしの規制や規則があって、東京市場の魅力は外国資本のみならず、国内の投資家にとっても魅力に乏しいありさまです。ここにも発想の転換と抜本的改革が必要です。最近、マスコミや報道に携る職員、並びに証券会社々員に依るインサイダー取引が発覚し、逮捕者が出ました。するとそれを以って直ちに規制強化に乗り出したりする風潮がありますが、問題の捉え方を全くはき違えております。世界に逆行する規制をすぐに編み出してゆく傾向にあります。一部の狼藉者、無法者を以って、全体を規制しようとする 狭隘な発想であります。時代の大きな潮流に逆行して改革、解放路線を封じ、官僚統制を敷いて、民活路線を封じ込めようとする妄想が直ぐに頭を持ち上げてくるのは慙愧に耐えません。
政界はもとより、法曹界然り、日進月歩の経済産業界然り、声高に改革を叫んで精鋭をつとめるはずの最高責任者が、いざ斯界に入ってしまうと期待にそむき、旧態然の体制に押されて埋没し、牙を抜かれて腑抜の体たらくに変じてしまうことは口惜しき限りではあります。
平成20年5月9日
社団法人 昭和経済会
理事長 ![]()